「ピアノが弾けないから保育士を辞めたい」
「保育士になりたいけどピアノが弾けない…」
このような理由で、保育士の道を諦めてませんか?
少しだけ、母について話させてください。
僕の母親は、保育補助という仕事に就いています。
保育士をサポートする仕事で、保育園によっては保育士とほぼ変わらない業務を任せられることもあります。
母は元々、別の仕事に就いていました。
ただ、年齢を重ねるごとに業務が辛くなったため、近場で働ける保育補助という選択肢を取りました。
そんな母親は、実のところ、この時点ではピアノを弾けない人だったんです。
今では母親もピアノを弾くことができ、子供の世話が楽しいと言って園児と撮った
この記事では、ピアノが弾けないことが理由で保育士を辞めたいと悩むあなたに向け、50歳を過ぎた初心者の母親がどのようにしてピアノを弾けるようになったのか、ご紹介します。
ピアノが弾けないから保育士を辞めたいと思っているならば、ちょっとだけ読んでみてください。
保育士の資格はピアノが弾けなくても取得できる!
実のところ、保育士の資格自体は、ピアノが弾けない人でも取得することができます。
保育士の国家資格は、「実技試験」と「筆記試験」に分かれており、筆記試験を受け合格した人が実技試験に進むという流れです。
実技試験は、「音楽」、「造形」、「言語」の3つの分野から2つを選び、試験を受けます。
音楽に関する分野が苦手な人は、実技試験で「造形」と「言語」を選択し試験を受けられます。
また、「音楽」を選択した場合でも、楽器の選択肢は3つあり、アコースティックギター・アコーディオン・ピアノのなかから選択します。
そのため、ピアノができなくても試験を受け合格するための選択肢はたくさんあるといえるでしょう。
保育士の資格試験は「筆記試験」と「実技試験」があります。
このとき、ピアノを弾くことになるのは、実技試験のときだけ。
しかも、その実技試験で「音楽」を選ばなければ、ピアノを弾かないで試験に臨めるのです。
また、筆記試験にてピアノに関する問題は出題されません。
「保育原理・子供の発達・社会福祉」などの知識がメインなので、ピアノスキルがなくても十分に合格を目指せます。
- 実技試験で「造形」と「言語」を選択する
- 「音楽」を選び、かつピアノ以外を選択する
さらに、実技試験で音楽を選んでピアノを演奏する場合、完璧な演奏は求められていません。
心を込めて演奏すれば、十分に評価されるのです。
このように、保育士の資格はピアノが弾けない人でも取れるのです。
結局はピアノの演奏が求められてしまうことも…
保育士の資格試験では、ピアノが弾けなくても問題ないことが分かりました。
では、保育士として実際に働き始めた場合はどうなのか。
まず、ピアノを演奏できなくても、保育士になることは可能です。
ただし、演奏を求められる機会があるため、弾けるに越したことはありません。
たしかに、保育園や幼稚園では、ピアノを弾く場面が日常的にあります。
ただ、求められるのはプロ並みの演奏ではなく「子供たちと一緒に楽しく歌える伴奏」です。
ピアノを弾けないなら、まずはシンプルな曲の練習から始めるのがおすすめ。
定番の動揺などは初心者にやさしい楽譜であり、簡単に弾けるようになります。
最近だと、カラオケ音源を使って歌を楽しむ園も増えており、ピアノを弾けない人のサポートも色々とあります。
とはいえ、ピアノが弾けると子供との距離感が縮むのは間違いありません。
「ピアノを弾けなくても大丈夫」と自分に言い聞かせつつ、少しずつ練習していきましょう。
初心者の母がピアノを弾けるようになった方法
50歳を過ぎて全くの初心者だった母が、どのようにしてピアノを弾けるようになったのか。
ここでは、ピアノが弾けないと悩むあなたに向けて、母が弾けるようになった方法を紹介します。
練習回数を増やせる環境に整える
母が真っ先に実施したことは、ピアノの購入でした。
とにもかくにもピアノの上達には練習を重ねるしかないので、購入した次第です。
「ピアノなんて高級品は変えない」
と思うかも知れませんが、母親が購入したのは電子ピアノです。
床やテーブルに置いて気軽に楽しめるタイプですね。
母親のゴールは、あくまでも小さい子供と一緒に音楽を楽しめるレベルなので、高価なピアノを買う必要がありませんでした。
7,000円程度で購入できる電子ピアノもあるので、もしも今ピアノを持っていないなら、ぜひ検討してみてください。
練習する曲を絞る
次に母親は、練習する曲を絞りました。
保育士に求められる演奏曲は、動揺などの簡単な曲です。
実用的な曲を弾けるようになることがゴールなので、それに絞って練習をひたすら繰り返してました。
最初のうちは手がおぼつかない母でしたが、元々が簡単な曲なので数日も経てば弾けるになっていましたね。
100曲以上が収録されている本もあるので、1冊だけ買えば十分です。
保育士におすすめのピアノ本5選!初心者でも楽しく弾ける楽譜を紹介
ピアノが上手な人に指導を受ける
母親が最後に取った行動は、ピアノが上手な人に指導を受けることでした。
実は、僕の姉は幼少から本格的にピアノをやってまして…
コンクールに参加したり、大学はピアノ関連で入学したりした人物です。
そんな姉から簡単な指導を受けることで、母は初心者を脱したのです!
これは、僕の好きな格言なのですが…
そのためには、まず専門家にアドバイスを貰うのが1番である。
というものがあります。
正体隠して90日で1億円稼ぐ億万長者企画
何が言いたいかというと…
困っていることがあるならば、その道のプロに聞いてしまうのが問題解決の近道ということ。
身近にいるピアノが上手な人に、練習を確認してもらってみてください。
きっと、今のあなたが躓いている部分を解決に導くアドバイスが貰えます!
ピアノ教室おすすめランキング|人気教室の料金・口コミ・特徴など比較
ピアノが弾けない不安を和らげる練習方法
ピアノを練習するとき、何から始めればいいか分からなくないですか?
でも大丈夫。
焦らず、できるところから少しずつ始めれば、ちゃんと上達しています!
ここでは、無理なく続けられる練習方法をご紹介します。
よく使う曲を厳選して練習する
保育の現場では、よく歌われる定番の曲がいくつかあります。
例えば「きらきらぼし」や「どんぐりころころ」などが有名ですね。
まずは、こうした簡単な童謡から練習を始めましょう。
よく使う曲だけでも覚えておくだけで、保育の現場で役立つ場面がグッと増えます!
また、シンプルなコードで構成されていることが多いので「両手で弾けなくてもまずは右手のメロディーだけ」でも十分。
慣れてきたら左手のコードをプラスしていくと、自然とレパートリーが増えていきます。
コード伴奏からスタートしてみる
「楽譜を読むのが苦手」という方には、コード伴奏がおすすめです。
コード譜はアルファベットで表記されていて、押さえる場所がわかりやすいのが特徴。
「C(ドミソ)」や「G(ソシレ)」など、基本のパターンを覚えてしまえば、様々なな曲に応用できます。
ピアノ初心者でも、コード弾きなら「それらしい伴奏」を作ることができますし、子供たちと一緒に歌うときにも十分なサポートになります。
「ピアノが弾けない保育士」の方でも、ちょっとした練習で驚くほど雰囲気が出せますよ!
スキマ時間で練習するコツ
忙しい保育士さんにとっては、まとまった練習時間を取るのが難しいことも多いですよね。
そんなときは、「スキマ時間」を活用するのがおすすめです。
例えば、朝の少しの時間や夜のリラックスタイムに、5分~10分だけでもピアノに触れる習慣をつけましょう。
短い時間でも毎日続けることで、自然と指が動くようになります。
無理なく続けることが、上達の近道です!
保育士向けピアノ教室を活用する
独学ではなかなか続けられない方や、効率よく学びたい方には、保育士向けのピアノ教室もおすすめです。
最近では、保育士の資格取得に向けた専用レッスンを提供しているピアノ教室も増えており、必要なポイントをしっかりと押さえた指導が受けられます!
先生にコツを教えてもらえると「ピアノが弾けなくても大丈夫」という安心感を感じられます。
実践的なアドバイスをもらいながら、自分のペースで無理なく上達していきましょう。
ここは、生徒のカウンセリングも実施しているので、もし今、悩まれているならおすすめですね。
保育士を目指すあなたに伝えたいこと
「ピアノが弾けない私に、保育士なんて無理かも知れない…」
そんなふうに悩んでいるなら、お伝えしたいことがあります。
ピアノに苦手意識があることは、別に悪いことではありません。
むしろ、多くの保育士さんが同様の気持ちを抱えてスタートしています。
大切なのは、子供たちと楽しい時間を作ること。
ピアノを弾く相手は、音楽の専門家ではなく子供たちです。
ミスタッチがあったとて、あなたが奏でる音楽に子供たちは歌ったり体を動かしたりしてくれます。
小学生でも両手で弾けるようになるのがピアノです。
保育士なのにピアノが弾けないと、悲観する必要はありません。
少しずつ練習すれば必ず弾けますし、その一生懸命な姿は子供たちの良いお手本になるはず。
「ピアノが弾けなくても大丈夫!」
この気持ちを忘れずに、臆せず挑戦してみてくださいね。
ピアノが苦手でも保育士の夢は叶う!
「ピアノが弾けなくても保育士になれますか?」
という不安を抱えていた方も、ここまで読めば前向きな気持ちになれたはず。
苦手意識があっても、基礎的な曲が弾けるようになると仕事の幅がグッと広がります。
子供たちと一緒に歌いながら伴奏ができる喜びも感じられるでしょう。
保育士に求められるのは「完璧なピアノ演奏」ではなく「子供と向き合う姿勢」です。
少しずつでもピアノに親しみ、自信を持って保育士の道を歩んでいきましょう。
あなたのその努力が、未来の子供たちの笑顔につながります。
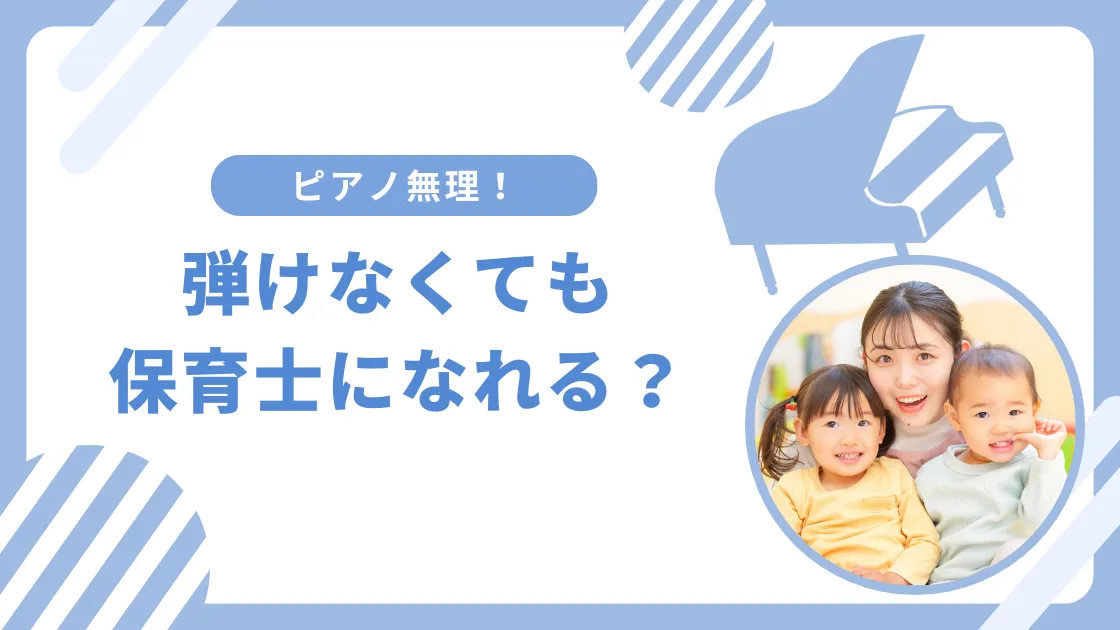
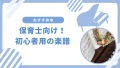
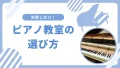
Comment コメントはこちらから